
ベーシック・ペンションの2050年までの実現を長期ビジョンの軸とする長期政治行政改革計画
2019年に端を発し、2020年、2021年とグローバルレベルで多大な影響を及ぼしている新型コロナパンデミック。
その経験を踏まえて、短期10年2030年、中期20年20340年、長期30年2050年という10年スパンで、安心・安全な日本国家と国民の安心・安全な暮らしを保障する社会創りのための長期ビジョンと戦略的重点政策体系をとりまとめ、その実現を図る遠大な取り組み計画を当サイトの発祥起源であり、親サイトでもある https://2050society.com で提案しています。
名付けて
「2050年国家ビジョンと長期政治行政改革計画」 シリーズ
これまでに、その軸となる以下の6記事を投稿しました。
◆ 異常な祭りの後に正常なまつりごとを:2021年起点に構築する2050年国家ビジョンと長期政治行政改革計画1ー2021年衆院選各党公約注視から(2021/7/21)
◆ 当サイト2050society.com の2021年下期カテゴリー変更:コロナ禍で構築すべき国家ビジョンと長期政治行政改革計画-2(2021/7/26)
◆ 国土・資源政策、社会政策、経済政策、国政政策4区分での長期ビジョン重点戦略試案 (2021/7/27)
◆ 国土・資源政策 2050年長期ビジョン及び短中長期重点戦略課題 (2021/8/1)
◆ 社会政策 2050年長期ビジョン及び短中長期重点戦略課題(2021/8/3)
◆ 経済政策 2050年長期ビジョン及び短中長期重点戦略課題(2021/8/5)
◆ 国政政策 2050年長期ビジョン及び短中長期重点戦略課題(2021/8/7)
「国土・資源政策」「社会政策」「経済政策」「国政政策」の4区分で構成するこの「2050年国家ビジョンと長期政治行政改革計画」。
それぞれについて、上記記事リストの終わりの4記事で提起したものを、今回、こちらにそのまま転載しました。
その意図は、全体の長期ビジョン及び政策の軸、目標の最重要戦略課題に、当サイトで提案の、日本独自のベーシックインカム「ベーシックペンション・生活基礎年金」の実現を据えていることをお伝えすることにあります。
ベーシック・ペンションは、一応「社会政策」の中に位置づけていますが、その制度の導入・実現に伴って、実に広範かつ重要な領域の政策課題に影響を与え、関連して制度・法律の改正が必要になります。
但し、そのほとんどの政策の必要性は、ベーシック・ペンションとは関係なく現状とこれからの日本社会に存在するものであり、これから取り組むべき課題として提起しています。
そして冒頭申し上げたように、それらの多くは、コロナパンデミックの経験から、必要性を学び取り、確認した課題でもあります。
以下、4区分ごとに転載したものを、ざっと確認頂ければと思います。
Ⅰ 国土・資源政策 長期ビジョン及び短中長期重点戦略課題
<長期ビジョン>
有限の国土及び各種資源の安全保障を守り、持続性を備えた可能な限りの自給自足国家を確立し、国民の命と安全・安心を守る国家政策の実現・追究を図る。
<短中長期・政治行政重点政策課題>
1.国土の安全保障・維持・総合管理
(基本方針)
有限な土地及び国土自然環境資源の安全を保障し、国民の日常生活の安心・安全を維持・確保するための基本的な政策を円滑に進め、2050年までに、望ましい日本の持続可能な国土の在り方と維持管理システムを創造・構築します。
(個別重点政策)
1-1 国土総合管理、有限土地活用のための規制・利用システム整備・確立
1)国土保有者及び利用状況現状調査及び分析(~2030年)
2)上記調査分析結果に基づく、土地利用総合及び都道府県別長期方針整備( ~2030年 )
3)同方針に基づく長期ビジョン、長期整備開発計画策定及び予算見積(~2035年)
4)上記長期計画及び予算に基づく実行・進捗・評価管理(1次~2040年、2次~2045年、3次~2050年)
1-2 防災・減災・復興長期計画、山林管理
1)危険地域等現状調査 (~2025年)
2)復興取組中地域現状調査及び再計画立案 (~2025年) 、予算策定、進捗・評価管理 (2031年~)
3)危険地域防災・減災対策立案及び予算策定 (~2030年) 、進捗・評価管理 (2031年~)
4)治水・山林計画立案及び予算策定 (~2030年) 、進捗・評価管理 (2031年~)
1-3 外国資本による土地及び建物等不動産取得禁止
1)海外資本及び外国人保有土地及び建物実態調査及び分析(~2025年)
2)海外資本及び外国人保有土地・建物対策検討、立案(含む予算化)(~2030年)
3)外国資本及び日本人以外の土地及び建物取得規制方針及び同法整備(~2030年)
4)上記法律施行(2)対策実行含む)(2031年~)
1-4 社会政策、経済政策、国政関連政策課題との統整合
※各政策策定後調整・統合
2.電力・エネルギー自給自足による安全保障・維持・開発管理
(基本方針)
気候温暖化・自然環境破壊などがもたらす国民生活、各種事業活動上の不安・悪影響を抑止し、将来に向けて持続可能な電力・エネルギー自給自足体制の整備、安心・安全を保障する同システムの構築を推進し、2050年までに100%再生可能エネルギー国家と水素社会を実現します。
(個別重点政策)
2-1 100%再生可能エネルギー及び水素社会の実現
1)各再生エネルギー別現状及び長期問題点・リスクなど調査及び分析( ~2030年 )
2)個人住宅及び事業所建物再生エネ発電・電源利用義務化及び支援法制化・施行(~2030年)
3)長期電源構成ビジョン及び長期計画策定(~2025年)、エネルギー危機管理システム策定 ( ~2030年)
進捗・評価管理 (2031年~) 、100%エネルギー自給自足国家化(~2050年)
4)水素エネルギー社会化技術開発調査及び長期計画・予算策定( ~2030年)
プロジェクト進捗・評価管理 (2031年~) 、(100%再生可能エネによる)水素社会実現( ~2050年)
2-2 電力送配電網の国有化と家庭用電力基本料金の無料化
1)現状電力送配電網問題点調査及び方針立案(~2025年)
2)送配電網国有化法制化及び予算化、移行・実行計画立案(~2030年)
3)電力会社等電力事業システム再構築(国・地方自治体・民間企業及び個人・一般企業)
4)家庭用電力料金無料化(2050年~)
2-3 GXグリーン・トランスフォーメーション推進、原子力発電の停廃止と完全安全技術転用
1)産業別・企業別GX推進計画策定 (~2030年) 、進捗・評価管理 (2031年~)
2)国家主導・支援GX推進計画・支援計画策定 (~2030年) 、進捗・評価管理 (2031年~)
3)必要原子力発電関連技術活用政策、長期計画策定 (~2030年)
4)原発停止方針確定、福島原発処理他廃棄物処理長期計画策定・予算化 (~2030年)
2-4 社会政策、経済政策、国政関連政策課題との統整合
※各政策策定後調整・統合
3.食料自給自足による安全保障・維持・開発管理
(基本方針)
コロナパンデミックや大規模自然災害など、さまざまなリスクに対応できる食料自給自足国家とその持続可能な社会システムを2050年までに構築し、その基盤の下にグローバル社会に貢献できる食料のサプライチェーンモデルも構築します。
(個別重点政策)
3-1 食料自給自足国家社会の拡充:農地実態調査、未耕作地集約、自治体別強化農産品目決定
1)食料品種別自給率調査及び長期自給率目標策定 (~2025年)
2)農地生産地実態調査、未耕作地等未利用地実態調査 (~2025年)
3)目標自給率実現品種・生産地域計画立案 (~2030年) 、都道府県別農産政策立案 (~2030年)、
取り組み進捗・評価管理(2031年~)
※最重点品目:小麦
4)食料品危機管理システム整備構築(~2030年)
3-2 農林畜産水産業の長期総合政策策定と持続的取り組み
1)畜産部門自給自足長期計画、振興支援計画策定、都道府県別計画策定 (~2030年) 、各進捗・評価管理
2)水産部門、遠洋・近海漁業保全計画策定、養殖分野長期計画策定 (~2030年)
3)グローバルサプライチェーン長期方針及び計画立案 (~2030年)
4)畜産物・水産物危機管理システム整備構築 (~2030年)
3-3 食品・飲料製造産業の水平・垂直統合
1)食品・飲料製造産業原材料調達・内外依存度等実態調査及び長期方針 (~2030年)
2)基礎食品・飲料指定化と自給自足可能度評価、対策立案 (~2030年)
3)都道府県別受給可能度調査及び緊急時国内サプライチェーン構築計画 (~2030年)
4)グローバルサプライチェーン長期方針及び計画立案(~2030年)
3-4 社会政策、経済政策、国政関連政策課題との統整合
※各政策策定後調整・統合
4.自然環境の安全保障と持続可能性管理
(基本方針)
有限の国土・自然環境のもと、環境保護・自然保全、観光・文化資源保全と有効活用などの政策を推進し、持続可能な仕組み創りを2050年までに実現します。
(個別重点政策)
4-1 カーボンゼロ政策推進
1)長期カーボンゼロ化計画策定 (~2025年) 、進捗・評価管理 (2031年~)
2)炭素税法制化・運用管理化 (~2025年) 、進捗・評価管理 (2031年~)
3)産業別・企業別カーボンゼロ化促進政策具体化 (~2030年) 、進捗評価管理 (2031年~)
4)環境・エネルギー政策との統整合
4-2 自然環境保全・保護・持続性確保長期整備
1)自然環境実態調査 (~2025年)
2)モデル自然環境保全保護計画策定 (~2030年)
3)環境政策課題体系化・総合化・個別計画立案、長期取り組み計画策定(~2030年)
4)再生可能エネルギー活用自然等との調整 (~2030年)
4-3 観光・文化資源の維持
1)観光・文化資源実態調査と保全方針・計画立案(国家レベル)
2)地域文化・伝統保全方針及び支援計画策定 (~2030年) 、進捗・評価管理 (2031年~)
3)国内観光・文化資源評価と維持・活用方針 (~2030年)
4)インバウンド観光・文化資源評価と維持・活用方針 (~2030年)
4-4 社会政策、経済政策、国政関連政策課題との統整合
※各政策策定後調整・統合
5.社会的インフラストラクチャーの安全保障・維持管理
(基本方針)
社会的公共資本に位置づけられる、水、電力・ガス、道路・通信等の「社会的インフラストラクチャー」の安全保障の見地から、その基盤の整備・拡充、安全・安心管理供給システム開発及び必要に応じて公共事業化を図り、持続可能な社会システムを2050年までに構築します。
(個別重点政策)
5-1 水資源対策、上下水道事業国公営化
1)治水事業・維持開発計画 (~2030年)
2)上下水道設備維持管理、現状調査及び長期整備計画立案 (~2030年) 、進捗・評価管理
3)全上下水道地方自治体事業システム化及び国家統括共通・共用システム開発 (~2030年)
4)水資源危機管理システム及び態勢整備 (~2030年)
5-2 電力供給網・ガス供給網維持、安定化
1)住宅用・産業用電力自給自足システム整備 (~2030年)
2)電力送配電網の国有化、管理システム開発・運用管理事業組織体制構築 (~2030年)
3)化石燃料ガス供給システムの高度の安全化 (~2030年)
4)化石燃料ガスの、再生エネルギー起源水素ガスへの転換促進 (~2040年)
5-3 道路交通網、通信網、全国民インターネット利用環境整備 全国民DX推進(端末配布)
1)道路交通網リスク調査と整備計画策定 (~2030年) 、取り組み進捗・評価管理
2)通信網リスク調査と整備計画策定 (~2030年)
3)インターネット・セキュリティ・システム総合開発管理計画策定 (~2030年) 、運用管理 (2031年~)
4)全国民インターネット・デジタル生活基盤整備:マイナカード、端末全員配布・保有(~2035年)、活用 (2036年~)
5-4 社会政策、経済政策、国家政治関連政策課題との統整合
※各政策策定後調整・統合
6.産業資源自給自足基盤の拡充による安全保障・維持・開発管理
(基本方針)
自然資源安全保障システムを整備確立する上で、関連する産業基盤、すなわち産業資源の一定レベル以上での自給自足を可能とする保全・開発を推進することが不可欠であり、必要な分野と品種・品目等に焦点を当て、2050年までにその目標とするレベルとシステムの実現を図ります。
(個別重点政策)
6-1 各分野資源保有率・保有年数等現状調査及び中長期方針構築
1)産業分野別・製品別自給率及び対外依存率調査・評価 (~2030年)
2)国内産業再編方針及び新規事業開発構想立案 (~2030年)
3)国内自給自足化戦略及び長期取り組み計画立案 (~2030年) 、進捗評価管理 (2031年~)
4)グローバル・サプライチェーン長期方針・計画策定 (~2030年) 、進捗・評価管理 (2031年~)
6-2 半導体国内自給自足体制構築
1)国内・海外供給体制調査、長期予測とりまとめ (~2025年) (定期的にメンテナンス)
2)国内産業・企業との長期方針、長期計画調整、支援計画(~2025年)
3)長期自給自足体制移行計画策定(~2025年)
4)グローバル・サプライチェーン長期方針・計画策定(~2025年)
6-3 レアメタル等希少資源の代替資源・技術開発
1)必須レアメタル等希少資源のグローバル調査及び将来予測 (~2025年)
2)国内調達可能必須レアメタル保有度評価と代替化可能性調査・評価、対策立案 (~2030年)
3)代替可能品開発支援計画及び予算策定(~2030年)
4)グローバル・サプライチェーン長期方針・計画策定(~2030年)
6-4 社会政策、経済政策、国政関連政策課題との統整合
※各政策策定後調整・統合

Ⅱ 社会政策 長期ビジョン及び短中長期重点戦略課題
<長期ビジョン>
すべての国民が、憲法に規定する基本的人権及び最低生活保障を受ける権利に基づいて制定され、所属する多様な社会・組織において享受し保障されるすべての社会保障・福祉政策の国家の不断の取り組みにより、安心と安全な暮らし、自由な働き方・生き方が選択できる社会モデルの構築・実現を図る。
<短中長期・政治行政重点政策課題>
1.社会保障・社会福祉制度改革
(基本方針)
日本独自のベーシックインカム、ベーシック・ペンション生活基礎年金制度の2040年までの導入、2045年までの修正定着をめどに、社会保障・社会福祉制度の総合体系の再構築と関連する法制の整備、関連行政組織及び業務改革を行い、種々の貧困・格差及び世代間不公平性・不満感の是正、平等・公正な社会活動の機会基盤の整備拡充と安全・安心な暮らしが持続できる社会を2050年までに形成します。
(個別重点政策)
1-1 社会保障制度体系改革
1)ベーシック・ペンション導入に伴う社会保障制度・福祉制度体系の再構築(~2040年)
2)社会保障制度改革:健康保険・介護保険制度統合、国民年金制度廃止・厚生年金制度改定、児童福祉・障害者福祉制度改正、生活保護制度対策他( 第一次~2030年、第二次~2040年、第三次 ~2050年)
3)労働政策・労働保険関連制度改革:労働基準法解雇規制改正、雇用保険法改正、非正規雇用転換制改正、最低賃金法改正、労災保険改正等 ( 第一次~2030年、第二次~2040年 、第三次 ~2050年 )
4)社会保険制度改革、世代間負担公平性対策、関連所得税改正、その他社会保障制度体系再構築に伴う関連法律の改定 ( 第一次~2030年、第二次~2040年 、第三次 ~2050年)
1-2 ベーシック・ペンション導入及び関連各種制度・システム包括的改定
1)日本独自のベーシックインカム、専用デジタル通貨JBPCによるベーシック・ペンション生涯基礎年金制度導入(~2040年)
2)ベーシック・ペンション導入に伴う関連諸制度・法律の改正・改革
3)ベーシック・ペンション確立までのベーシックインカム段階的導入(第一次~2030年、第二次~2040年)
4)ベーシック・ペンション導入のための日本銀行改正、JBPC発行・管理システムの開発・運用化 (~2040年)
1-3 社会保障・社会福祉行政改革(公的サービス事業公営化促進、公務員化)
1)ベーシック・ペンション導入、社会保障制度体系改革に伴う行政官庁再編、組織・業務改革 (第一次~2030年、第二次~2040年、第三次~2050年)
2)国・公営サービス事業再編:利益追求型社会サービス事業の一部国公営事業転換、社会福祉法人等の再編 (第一次~2030年、第二次~2040年、第三次~2050年)
3)社会保障・福祉資格制度の拡充、キャリアプログラム開発 (第一次~2030年、第二次~2040年)
4)社会保障・福祉関連職公務員制度改革 (第一次~2030年、第二次~2040年)
1-4 国土・資源政策、経済政策、国家政治政策関連政策課題との統整合
※各政策策定後調整・統合
2.保育政策・子育て支援政策、少子化対策・こども貧困対策
(基本方針)
長期化し、歯止めがかかっていない出生率低下・出生数減少、少子化対策の抜本的な見直しを、2050年人口1億人への人口減少社会を想定して行い、目標とする社会の実現を図る。
それと並行して、安心して子どもを産み、育てることが可能な保育政策・子育て支援政策を、社会的共通資本政策として強力に推進し、近年の子どもと家族をめぐる社会問題の改善・解消を2050年までに実現します。
(個別重点政策)
2-1 少子化対策、人口減少社会対策
1)経済的支援ベーシック・ペンション導入による婚姻率・出生率向上(児童手当制度廃止拡充転換を伴う) (第一次~2030年、第二次~2040年、第三次~2050年)
2)保育制度・保育行政改革、子育て支援システム拡充による総合的少子化政策推進 (第一次~2030年、第二次~2040年)
3)地域別(都道府県別)少子化対策取り組み策定と国による支援 (第一次~2030年、第二次~2040年)
4)長期人口減少社会計画策定(国家及び地方自治体)と取り組み・進捗評価管理(人口構成、外国人構成等) (第一次~2030年、第二次~2040年、第三次~2050年)
2-2 保育制度・保育行政
1)5歳児(~2030年)・4歳児(~2035年)保育の義務化
2)保育施設再編及び同行政組織再編(第一次~2030年、第二次~2040年)
3)学童保育システム確立、待機児童問題解消 (第一次~2025年、第二次~2030年)
4)保育士職の待遇、労働環境・条件など改善 (第一次~2025年、第二次~2030年)
2-3 子育て支援システム
1)地域包括子育て支援センター組織・業務機能拡充 (第一次~2025年、第二次~2030年)
2)子どもの貧困解消総合政策(ベーシック・ペンション児童基礎年金導入他) (第一次~2030年、第二次~2040年)
3)孤育、ひとり親世帯、孤立世帯支援行政システム・体制整備拡充 (第一次~2025年、第二次~2030年)
4)関連NGO等民間地域ネットワーク拡充支援 (第一次~2030年、第二次~2040年)
2-4 国土・資源政策、経済政策、国家政治政策関連政策課題との統整合
※各政策策定後調整・統合
3.教育制度改革
(基本方針)
次世代を形成する児童・学生への期待は、教育機会の平等、教育格差の是正、学校や教育システムなどのインフラを経済的な不安なしで利用できる制度など、社会的共通資本としての教育制度・教育政策基盤が整備され、提供されて初めて、積極的な行動を求めることができるものです。
そのために必要なさまざまな制度の体系と方法を再構築し、自身の希望や困難に挑戦し克服する姿勢・能力・技術の向上や自己実現・社会貢献に結びつく多様な個性・人間性そして人生の実現の支援政策を推進します。
(個別重点政策)
3-1 義務教育改革
1)5歳児・4歳児義務保育制導入 (第一次~2030年、第二次~2035年)
2)教育格差改善・解消対策、学童保育問題、いじめ・自死対策 ( 第一次~2030年、第二次~2040年 、第三次 ~2050年 )
3)新教育基本法改正、教科・教育方法改訂 ( 第一次~2030年、第二次~2040年 、第三次 ~2050年 )
4)教員支援改革 ( 第一次~2030年、第二次~2040年 、第三次 ~2050年 )
3-2 高等学校教育改革
1)高等教育改革(高校専門教育課程・専門高校多様化拡充) ( 第一次~2030年、第二次~2040年 、第三次 ~2050年 )
2)起業・経営専門スキル、IT、AIスキル教育課程拡充 ( 第一次~2030年、第二次~2040年 、第三次 ~2050年 )
3)学生交流・交換留学等教育国際化推進 ( 第一次~2030年、第二次~2040年 、第三次 ~2050年 )
4)ベーシック・ペンション学生等基礎年金、特別供与奨学金制度による経済的支援 ( 第一次~2030年、第二次~2040年 、第三次 ~2050年 )
3-3 大学・大学院教育改革、留学・社会人教育、生涯教育基盤拡充
1)大学・大学院教育改革、大学・大学院組織改革、研究者支援システム改革 ( 第一次~2030年、第二次~2040年 、第三次 ~2050年 )
2)(無償供与)特別奨学金制度 (~2030年)
3)留学制度拡充支援、グローバル大学育成 ( 第一次~2030年、第二次~2040年 )
4)社会人キャリア開発、高度専門スキル開発教育支援、生涯学習基盤整備拡充 ( 第一次~2030年、第二次~2040年)
3-4 国土・資源政策、経済政策、国家政治政策関連政策課題との統整合
※各政策策定後調整・統合
4.ジェンダー問題政策
(基本方針)
多様性(ダイバーシティ)自体の多様化・複合化が進展するなか、一向に改善されない日本社会、政治・行政領域、企業社会、地域社会におけるジェンダー問題。
その遅々たる状況は、政治行政政策における転換がなされない限り、グローバル社会における先進国評価とのギャップが拡大する一方であることはこれまでの空白の30年で証明されています。
スローガン型の「やっている感」政治行政からの脱却・転換を共通認識とし、5年・10年スパンでの望ましい変化を評価確認できる行動計画と関連法制化計画を提示し、推進・実現します。
(個別重点政策)
4-1 ジェンダーギャップ改善政策
1)総合的ジェンダー政策策定(~2025年)
2)ジェンダー多様性個別政策(LGBTQ、関連分野別)( ~2025年)
3)公的個別課題目標値設定及び達成計画立案 ( ~2025年) 、進捗・評価管理(2026年~)
4)民間個別課題目標値設定及び達成計画立案 ( ~2025年) 、進捗・評価管理(2026年~)
4-2 男女雇用・労働格差対策
1)育児・介護支援制度、同休業制度拡充等労働政策改善・拡充(~2030年)
2)男女雇用・賃金処遇差別対策(採用、非正規雇用、正規雇用転換、同一労働同一賃金等) (第一次~2030年、第二次~2040年)
3)労働基本法関連格差是正対策 (第一次~2030年、第二次~2040年)
4)職場ハラスメント等企業行動規範問題等対策 (~2030年)
4-3 家族・夫婦間ジェンダーギャップ社会問題政策
1)夫婦別姓問題、同性婚問題対策・改善 (~2030年)
2)共同親権問題、養育義務不履行問題、DV問題対策・改善 (~2030年)
3)家庭内性別役割分業問題改善 (~2030年)
4)その他ジェンダー問題改善(性行動、性転換他)(~2030年)
4-4 国土・資源政策、経済政策、国政政策関連政策課題との統整合
※各政策策定後調整・統合
5.高齢化社会政策・介護政策
(基本方針)
団塊の世代を形成するすべての高齢者が100歳を超えている2050年には、現状の高齢化社会は、総人口の減少及び年齢構成の大きな変化を伴って新たな状況を迎えます。
それに伴って、社会保障制度の体系と実際の制度・法律も、その状況にふさわしいものに整備され、確立されていることが求められます。
今後進行する、世代継承・世代交代を念頭に、それまで続く高齢者の医療・年金問題、現役世代が抱く高齢世代への不満等の改善・解消に、当区分の<社会政策>で連携して取り組み、現役高齢者が安心・安全な暮らしを送ることができるよう、政治行政政策課題化して取り組みます。
(個別重点政策)
5-1 高齢者年金制度
1)ベーシック・ペンション導入に伴う高齢者年金制度改革:国民年金制度廃止、生活基礎年金支給、厚生年金制度改正(第一次~2030年、第二次~2040年)
2)厚生年金保険制度の賦課方式から積立方式への転換(第一次2031年~、第二次2036年~)
3)全給与所得者の厚生年金保険加入制度化(2031年~)
4)遺族年金制度改定(2031年~)
5-2 健康保険制度・介護保険制度改革、介護行政改革
1)後期高齢者医療保険・介護保険制度統合による高齢者医療介護制度改革 (第一次~2030年、第二次~2040年)
2)介護保険制度改正 (第一次~2030年、第二次~2040年)
3)老人施設事業運営改革 (第一次~2030年、第二次~2040年)
4)全給与職者の健康保険加入制へ (第一次2031年~、第二次2036年~)
5-3 高齢者生活、高齢者就労支援政策
1)地域包括高齢者支援センター拡充(高齢者夫婦世帯支援、単身高齢者世帯支援、高齢者施設等入所支援) (第一次~2030年、第二次~2040年)
2)高齢者生涯設計支援制度拡充(公的後見人制度、相続問題支援等) (~2030年)
3)健康寿命、認知症対策等支援 (第一次~2030年、第二次~2040年)
4)高齢者就労支援システム拡充 (第一次~2030年、第二次~2040年)
5-4 国土・資源政策、経済政策、国政政策関連政策課題との統整合
※各政策策定後調整・統合
6.各種社会問題克服政策
(基本方針)
いとも簡単に首相や政権政党から発せられる「自助」。
まともに自助努力を行う基盤そのものを持ち得ない現状の社会と社会システムを認識しない政治行政の無策の長期化が、少しずつ理不尽な分断行動と認識を増大しつつあります。
その結果でもあり、原因でもある、いじめその他のハラスメント・自殺・引きこもり、各種人権問題など、根深い要因を持つさまざまな社会問題と生きづらい個々人の人生・生活の改善・解消に、地道に、粘り強く取り組むことを課題とし、継続して、着実に改善・解消に結びつける取り組みを具体的計画化・スケジュール化して共有・公開し、取り組みを推進します。
(個別重点政策)
6-1 貧困・格差対策
1)総合貧困・格差問題対策調査・策定
2)個別貧困・格差問題取り組み方針・計画立案、進捗・評価管理
3)個別貧困・格差指標及び目標値設定、進捗・評価管理
4)生活保護制度政策、障害者福祉・児童福祉制度政策
6-2 いじめ、ハラスメント、孤立問題、自殺問題対策
1)いじめ他各種ハラスメント撲滅対策
2)孤立・引きこもり、孤独社会対策(自殺問題含む)
3)誹謗中傷対策、フェイク情報問題
4)各種人権問題
6-3 刑事・民事犯罪抑止対策
1)特殊詐欺対策
2)サイバー、インターネット犯罪対策
3)個人情報対策
4)緊急時・非常時権利制限政策、凶悪犯罪対策
6-4 国土・資源政策、経済政策、国政政策関連政策課題との統整合
※各政策策定後調整・統合

Ⅲ 経済政策 長期ビジョン及び短中長期重点戦略課題
<長期ビジョン>
行き過ぎた資本主義の弊害、それと関連するグローバル経済がもたらす地球温暖化・環境破壊問題などへの抜本的な取り組みを必須課題とし、それと並行して進める望ましい経済活動のモデルを、経済の安全保障の観点から国内経済で確立することを所期の目標とし、そのモデルのグローバル社会への移転・移管と支援に結びつけることを併せて目標とする。
<短中長期・政治行政重点政策課題>
1.自給自足経済政策
(基本方針)
コロナパンデミックで経験した物流・人流の停止等の経験、また国家間の力学的な問題等から想定すべき、経済の安全保障ニーズに基づき、まずその基本である国内で還流・循環する自給自足経済の確立を目指し、確実に実現します。
(個別重点政策)
1-1 食料自給自足経済確立:「国土・資源政策」 3.食料自給自足による安全保障・維持・開発管理 と連携
1)第6次産業化含む包括的総合的食料(飲料含む)国内自給方針及び中長期目標策定、ベーシック・ペンション導入時利用構成比率シミュレーション及び対策
2)品種・品目別原材料依存率・国内対応率等実態調査及び方針策定
3)品種・品目別国内自給率目標設定と必要財政政策・計画立案
4)農業・畜産業・水産業自給自足産業構造構築(全国及び地域別、緊急時供給体制等含む)
1-2 生活基礎消費財自給自足経済化
1)業種別必要品種・品目調査分析(対外依存状況、国内対応状況等含む)
2)業種別必要品種・品目別国内自給方針及び中長期目標策定、ベーシック・ペンション導入時利用構成比率シミュレーション及び対策
3)地域別・地域間サプライチェーン整備、緊急時体制整備
4)緊急時海外供給体制整備
1-3 全産業分野基礎物品自給自足経済化(サプライチェーン構築)
1)緊急事態想定時全産業分野におけるリスク調査・分析(3年毎の見直し)
2)同調査・分析に基づく総合的短中長期対策立案(~2030年)、進捗・評価管理(~2031年)
3)同調査・分析に基づく産業別・品種品目別国内対策立案 (~2030年) 、進捗・評価管理 (~2031年)
4)「国土・資源政策」 6.産業資源自給自足基盤の拡充による安全保障・維持・開発管理 と連携
1-4 国土・資源政策、社会政策、国家政治政策関連政策課題との統整合
※各政策策定後調整・統合
2.雇用政策・労働政策
(基本方針)
長期化するデフレ経済から脱却し、国民がより豊かな経済的基盤を確立し、安心・安全・自由な生き方、働き方ができるよう、自らの起業を含む労働と就労・雇用に関する制度と法律の改正・整備拡充を推進します。
なお、当政策は、「社会政策」の軸とした<ベーシック・ペンション>の実現と連携した政策と位置づけていますが、<ベーシック・ペンション>の実現の有無に拘らず取り組むべき政策として設定するものです。
(個別重点政策)
2-1 非正規雇用法制改革、労働者派遣法制改正
1)非正規雇用の正規雇用転換制度の拡充
2)労働者派遣法改正:派遣職種の制約強化
3)同一労働内容職務同一賃金制整備拡充
4)非正規雇用者の各種労働条件の正規雇用者との平等化拡充
2-2 雇用保険制度の就労保険制度への転換・改定、解雇規制改定
1)雇用保険制度の就労保険制度への転換、全就労者の保険加入義務化
2)ベーシック・ペンション導入に伴う雇用保険改正
3)解雇規制の拡充強化、労働基準法関連条項改正
4)労働者災害補償保険法、その他労働法制改正
2-3 低賃金労働・違法労働対策:最低賃金法、エッセンシャルワーク賃金改善
1)最低賃金法改正
2)エッセンシャルワークの賃金制度改革支援及び推進
3)違法労働、ブラック企業等撲滅対策
4)中小企業人事労務改善支援
2-4 国土・資源政策、社会政策、国政政策関連政策課題との統整合
※各政策策定後調整・統合
3.経営・事業開発支援、労働生産性・付加価値創造支援政策
(基本方針)
国民の安心・安全で自由な生き方・働き方や国政による種々の政治行政活動を可能にする経済活動は、種々の規律・規定のもと、健全な運営と管理により、必要なコストを負担し、適正な利潤を獲得することを目的とし、持続することが求められます。
個人の起業・独立から、零細中小企業、大企業、グローバル企業、それぞれがめざすもの、その活動規模などに違いはありますが、国家と個人、そして企業等の資産・資本を形成する基盤としての経済活動を公正・公平に支援する社会経済基盤を整備拡充します。
(個別重点政策)
3-1 起業・創業・独立支援政策
1)起業・独立及び企業経営専門教育の中高等教育課程組み入れ
2)起業・創業・独立経営の税制等緩和、各種支援インフラ整備
3)採用・人材育成・経営管理等支援インフラの整備、運営管理(官民協同)
4)M&A 支援インフラの整備、運営管理( 官民協同)
3-2 中小零細企業生産性・付加価値向上支援
1)中小零細企業人事労務・経営管理・資本管理等支援インフラの整備、運営管理
2)中小零細企業労働生産性・付加価値向上支援
3)中小零細企業の事業規模拡大・海外進出支援インフラ拡充
4)資本強化・M&A等支援インフラの整備、運営管理( 官民協同)
3-3 グローバル企業支援
1)業種・品種別グローバル企業展開支援政策
2)地域別グローバル企業展開支援政策
3)既存海外資本国内進出企業政策
4)国内進出海外資本企業政策
3-4 国土・資源政策、社会政策、国政政策関連政策課題との統整合
※各政策策定後調整・統合
4.イノベーション支援、技術開発支援
(基本方針)
DX、GX、ESG、 SDGsと、社会生活・職業・企業経営・社会経済と環境をめぐる技術開発、イノベーションニーズの加速化・拡大化が、グローバルレベルで進んでいます。
その取り組みは、個々の企業努力だけでは差別化も競争力も持ち得ず、国策としての総合的かつ的確なターゲット設定による対策・政策が不可欠です。
経済の安全保障にとどまらず、国民と国家社会のすべての活動と領域に影響を及ぼし、他のすべての政策と結びついているイノベーション、技術開発支援政策を、産官学の強力な連携に基づき推進します。
(個別重点政策)
4-1 イノベーション・技術開発中長期計画支援政策
1)産業別・技術領域別イノベーション・技術開発支援対象抽出設定及び支援計画策定
2)地域別イノベーション・技術開発プロジェクト制導入(地方自治体主管)
3)特許管理
4)人材育成、研究開発組織開発支援
4-2 DX、GX、ESG、SDGs総合政策
1)DX関連目標指標・重点支援事業領域設定 (~2025年) 、 進捗・評価管理 (2031年~)
2)GX関連目標指標・重点支援事業領域設定(~2025年) 、 進捗・評価管理 (2031年~)
3)ESG関連目標指標・重点支援事業領域設定(~2025年)、進捗・評価管理 (2031年~)
4)SDGs関連目標指標・重点支援事業領域設定 (~2025年) 、 進捗・評価管理 (2031年~)
4-3 産官学プロジェクト政策
1)大学間技術開発ネットワーク化
2)地方自治体間開発ネットワーク化
3)経済界共同プロジェクトネットワーク化
4)産官学統合プロジェクトマネジメント
4-4 国土・資源政策、社会政策、国政政策関連政策課題との統整合
※各政策策定後調整・統合
5.成長・脱成長、緊縮・反緊縮多様性モデル対応政策
(基本方針)
行き過ぎた資本主義や過剰な化石燃料エネルギー消費等を因とする貧困・格差の拡大や地球環境破壊、気候変動、大規模自然災害・厄災等。
こうした状況の継続・拡大とその基盤としての社会経済の変貌は、新自由主義的あるいは独裁主義的政治論点による成長・脱成長、緊縮・反緊縮イデオロギー対立を煽っています。
その多面的な社会経済状況を把握・分析し、 それぞれの利点を活かすことで、望ましい経済運営を可能とする経済政策の実行・実現に結び付けます。
(個別重点政策)
5-1 人口動態対応中長期経済成長モデル構想と短中長期対応計画
1)人口動態対応労働人口・労働力基本計画
2)職種・職能別・技術別必要労働力基本計画及び養成計画立案、支援
3)IT・AI活用業務領域予測及び推進計画に基づく職業・職種・雇用政策対応
4)人口動態対応地域別成長産業政策推進
5-2 緊縮・反緊縮、成長・脱成長経済モデル構想と短中長期対応計画
1)緊縮・反緊縮経済モデル構想化及びシミュレーションに基づく経済政策研究活用
2)成長・脱成長経済モデル構想化及びシミュレーションに基づく経済政策研究活用
3)業種別変化・転換予測等に基づく産業構造、経済政策変革研究開発
4)AI社会時社会経済環境予測と雇用・労働政策転換対応
5-3 ベーシックインカム(ベーシック・ペンション)導入シミュレーションと現実対応
1)多様機能ベーシック・ペンション導入経済政策モデル研究開発
2)ベーシックインカム(ベーシック・ペンション)段階的導入時経済動向シミュレーション及び対策モデル化
3)ベーシックインカム(ベーシック・ペンション)導入後社会経済行動調査分析及び活用
4) ベーシックインカム(ベーシック・ペンション)導入後社会経済モデル実現評価・分析
5-4 国土・資源政策、経済政策、国政政策関連政策課題との統整合
※各政策策定後調整・統合
6.グローバル経済政策
(基本方針)
経済の安全保障は、国内自給自足経済の整備だけで完結するものでは当然ありません。
グローバル社会における自国のポジションや存在意義を的確に自覚・確認し、自国の安全保障にとどまらず、グローバル社会経済においてのリーダーシップや協調・貢献をも実現すべく、長期ビジョンのもと取り組みます。
(個別重点政策)
6-1 経済安全保障政策
1)対外経済総合政策及び国別政策
2)輸出入管理政策
3)外国為替法管理政策
4)経済安全保障緊急時対策
6-2 グローバル経済収支政策
1)海外投融資政策
2)外為政策、外貨準備政策
3)国内経済・国外経済バランス政策
4)各種グローバル経済指標・情報収集分析・活用
6-3 グローバル金融・財政体制改革及び貢献方針
1)IMF改革提案
2)G7、G20等におけるプレゼンス強化とリーダーシップ発揮
3)各国中央銀行との協調等
4)グローバル通貨政策協調・開発等
6-4 国土・資源政策、経済政策、国政政策関連政策課題との統整合
※各政策策定後調整・統合

Ⅳ 国政政策 長期ビジョン及び短中長期重点戦略課題
<長期ビジョン>
国民国家としての日本のすべての国民と多様に機能する社会組織の安心・安全で豊かな生活と諸活動を保障する憲法を基軸とする司法・立法、同様支援する国家政治・行政及び地方自治・行政などの望ましい在り方を民主主義と法の下の平等と支配に基づき、継続して追究し実現すると共に、併せてグローバル社会において貢献する。
その必要性は、コロナパンデミックの経験を通して、より強く認識され、求められることとなり、当政策のすべてにおいてグローバルな視点での取り組みが必須であることを確認しておきたい。
<短中長期・政治行政重点政策課題>
1.内閣・行政改革
(基本方針)
人間の本質的な不完全性と権力・権益に対する欲求と麻痺により、その時代、その社会において政権と政治に種々多大な誤りや横暴が表出し、社会問題を長期化しかつ拡大させます。
そうした政治状況からの回復・修正を、都度、早期に図り、望ましい政治が継続して行われるよう、常に政治の基幹システム・制度の見直し・改善を行うべく、改革の先鞭を務め、他の3区分の政策の円滑な推進に結び付けます。
(個別重点政策)
1-1 衆議院解散権、内閣改造権等改正
1)衆議院解散権制約へ改定
2)内閣改造権制約へ改定
3)首相多選禁止制導入
4)首相権限見直し
1-2 内閣府機能改革
1)内閣人事局機能改正
2)内閣法制局機能改正
3)内閣官房機能改正
4)危機管理内閣法制整備
1-3 国家行政組織・業務改革、国家公務員法改正
1)行政組織再編成・改革(縦割り既得権型行政打破、横断的行政業務組織責任システム整備等)
2)行政業務システム改革(IT化、デジタル化、共通ソフト・プラットフォーム化等)
3)内閣・行政システムセキリティ対策
4)国家公務員法改正(国家公務員業務過失等保険制度導入、天下り禁止法拡充等)
1-4 国土・資源政策、社会政策、経済政策関連政策課題との統整合
※各政策策定後調整・統合
2.立法・司法改革
(基本方針)
内閣・行政改革は、そのほとんどすべてが、法律の改廃に基づき進めることとなります。
その手続きが速やかに、かつ適切に行われ、守られるためには、立法及び司法が果たすべき役割が適切に果たされるよう、そのシステム・制度もまた適切・的確に維持改善される必要があります。
そのための課題を、短期・中長期種々の必要性に応じて設定し、優先順位をつけて取り組み、望ましい在り方を継続して追究していきます。
(個別重点政策)
2-1 国会法改正、一院制改革
1)参議院廃止による衆議院一院制化
2)衆議院議員数変更、任期6年制、3年毎の改選方式
3)性別・年代別議員構成制確立
4)選挙制度改定(選挙区・比例制等、供託金制度改定)
2-2 基本的人権関連法改正
1)基本的人権としてのベーシック・ペンション明確化と導入(2050年までに憲法に明記)
2)社会政策による基本的人権領域の拡充と法制拡充
3)基本的人権としての個人情報管理法制整備
4)危機管理・緊急体制時の個人の基本的人権保護制の明確化
2-3 憲法改正、憲法審査会制拡充
1)2050年までの憲法改正、段階的憲法改正推進計画化・進捗管理
2)憲法審査会拡充
3)国民投票法改正
4)裁判制度改革、司法制度改革
2-4 国土・資源政策、社会政策、経済政策関連政策課題との統整合
※各政策策定後調整・統合
3.財政改革・金融改革
(基本方針)
現状の行政を司る機構・機能として財務省が非常に大きく、後半な権限をもち、それが、国政行政と地方行政の改革が進まない要因の一つとなっている共通認識があります。
その根源は、財務省の既得権益を守る体質にあることから、まず財務省とその業務領域と権限・権益の改革の先鞭をつけることは絶対条件といえるでしょう。
加えて、社会政策の根幹と位置づけるベーシック・ペンションの導入は、同時に従来の財務政策、財務省権益の展開、加えて日本銀行の機能改革と一体化してのものであり、それは財政改革及び金融改革につながるものになります。
(個別重点政策)
3-1 財政規律主義改革
1)財政規律主義見直し
2)税制体系改革
3)政府会計システム、財政システム改革
4)監査機能・権限拡充
3-2 日本銀行法・銀行法改革
1)ベーシック・ペンション導入に伴う日本銀行法改定
2)信用創造制約に関する銀行法改定
3)日本銀行機能改革
4)金融システム改革(デジタル通貨発行他)
3-3 財務省改革、歳入・歳出庁設置
1)財務省及び同省所管官庁の再編
2)歳入庁、歳出庁創設
3)地方自治体財政機能改革
4)長期国家財政ビジョン・計画策定
3-4 国土・資源政策、社会政策、経済政策関連政策課題との統整合
※各政策策定後調整・統合
4.地方自治・地方行政、地方財政
(基本方針)
地方分権の必要性が叫ばれ続けていますが、一向にその変化・進展は見られません。
これも国政機能の既得権益の保持・独占欲に基づくためですが、その打破、改革には、先述した国政行政、立法っして財政各改革が先行してこそ実現可能となります。
そのために、先行する各政策での改革実現と並行して、あるべき地方自治・地方行政・地方財政を追究し、実現に取り組みます。
(個別重点政策)
4-1 地方自治体財源改革
1)現状所得税の一部を個人住民税と住民所得税に統合し、地方財源拡充
2)地方交付税給付目的の一部に、国土・資源政策、社会政策、経済政策各個別政策充当規定化
3)地方債発行権限拡充、地域通貨発行権拡充、ふるさと納税改定
4)複数住民登録制に基づく第2地方税制導入
4-2 地方自治権再構築
1)都州制導入、州自治制構築、州知事権限確立(東京神奈川1都、北海・東北・北関東・東関東・北陸・甲信越・東海・関西・中国・四国・九州・沖縄10州制)
2)国家官庁地方出先機関と県単位自治機能の統合再編
3)県単位自治権、市区町村自治権改定(財源・行政改革と統合)
4)地方自治単位住民投票制の拡充
4-3 地方行政改革、地方公務員法改正
1)地方議会構成・構造改革(過疎地域の自治体議員要件改定、特定自治体地域の就労条件改正、地方行政組織改革、地方議会女性議員比率の人口比例実現等)
2)保育・障害者福祉・介護等社会保障福祉サービス事業の公営制転換、エッセンシャル・ワークの公務員化
3)非正規地方公務員の正規雇用化、社会保障福祉職能キャリア横断的開発制度化
4)地方公務員法改正
4-4 国土・資源政策、社会政策、経済政策関連政策課題との統整合
※各政策策定後調整・統合
5.外交、防衛・安全保障
(基本方針)
社会分断の一因でもある安全保障問題、核問題が、先述した各国政課題の停滞、改善改革の先送りに繋がっているという側面があります。
その認識を共通して持つことができれば、他の3大区分の政策は切り離して先行して協調して取り組み余地も広がるでしょう。
その上で、一朝一夕で結論を出すことが困難な当政策に、必要な時間を費やし、かつ緊急事態に当たっては共通認識をもって早期に対応しつつ、根本的な相違点において共有できる点、あるいは妥協点を見出し、具体化できるよう取り組みを進めたいと思います。
(個別重点政策)
5-1 長期外交方針
1)国際協調組織政策
2)国家体制別及び地政学的外交政策
3)国家別外交方針及び政策
4)外交エキスパート養成、情報関連機関の整備・拡充
5-2 長期安全保障・防衛構想構築、緊急時政策
1)長期国家安全保障政策、核政策
2)長期国家防衛方針・政策
3)グローバル社会安全保障政策
4)国家緊急事態時政策・法制整備
5-3 移民・難民政策
1)就労目的外国人法制の拡充
2)移民政策の見直し、確立
3)難民政策の見直し、確立
4)日本国籍取得関連法の改正
5-4 国土・資源政策、社会政策、経済政策関連政策課題との統整合
※各政策策定後調整・統合
6.グローバル社会、国際協調・協力
(基本方針)
コロナパンデミック後の国政と国民生活の在り方を考える前提として、国と国民の種々の安全保障の視点を軸に据えました。
それは決して自国ファーストの保守・保護主義をめざすものではなく、まず自国・自国民のそれを実現し、そのノウハウ・制度を、一つのモデルとして、グローバル社会に移転・紹介・支援することをも理想としています。
しかし、現状の種々の国際組織とその機能には硬直性や既得権国の独善性、非民主制も見られ、多くの改善・改革の必要性があります。
こうした問題への改善・解決にも積極的に取り組み、リーダーシップを発揮し、貢献することをめざすものです。
(個別重点政策)
6-1 国際組織協調・協力関係再構築
1)各種国際組織・機関方針見直し、再構築活動展開と貢献
2)国際連合改革促進
3)グローバル核政策主導及び貢献
4)グローバル環境政策主導参画及び貢献
6-2 先進国間協調政策
1)自由主義・民主主義先進各国との政策協調
2)独裁主義・反民主主義先進国家政策
3)異常時・緊急時協調国家間対応システム構築
4)新グローバル秩序構築推進・貢献
6-3 後進国支援・協調政策
1)後進国支援方針・ビジョン・長期計画策定、進捗・評価管理
2)モデル社会経済政策・システム移管協力
3)国家間人的・技術的交流促進
4)支援プログラム・支援方式開発及び展開
6-4 国土・資源政策、社会政策、経済政策関連政策課題との統整合
※各政策策定後調整・統合

今秋の衆議院選以降を見据えて
この後は、主に課題項目レベルに留まっている個々の課題・政策を、都度折々の話題や情報などを元に取り上げ、その内容を具体化していきます。
例えば、昨日その1回目として、以下を投稿しました。
◆ 脱炭素、グリーントランスフォーメーション(GX=緑転)4つの課題(2021/8/10)
これは、「国土・資源政策」及び「経済政策」の中に設定された政策課題項目に関する1つというわけです。
なお、これも今まで繰り返し申し上げてきていますが、理想とするベーシック・ペンションの実現には相当の時間・年数がかかると考えています。
(参考)
◆ ベーシック・ペンション実現は10年がかりの夢、団塊の世代から次世代へのレガシーとして(2021/2/8)
◆ ベーシック・ペンション実現に10年を想定する4つの理由(わけ) (2021/3/4)
しかし種々の社会問題を考えると、実際には1日でも早期にベーシック・ペンションの実現が必要と思っており、種々の意見を参考に、可能な範囲で、少しずつでも部分的ベーシックインカムとして導入することが望ましいわけです。
そこで、最近以下の提案も行っています。
(参考)
◆ 全員月額7万円で始める:ベーシックインカム現実的実現法考察-1(2021/7/17)
◆ 月額7万円ベーシックインカムの条件と期待効果:ベーシックインカム現実的実現法考察-2(2021/7/18)
◆ 無理なく、漸進的・段階的に導入するベーシックインカム:ベーシックインカム現実的実現法考察-3 (2021/7/19)
◆ 7万円現金給付ベーシックインカムの次にデジタル通貨ベーシック・ペンションを:ベーシックインカム現実的実現法考察-4 (2021/7/28)
いずれにしても、現状の政治を考えるとき、今秋の衆議院選挙での各政党の政策や綱領をみると、どこもベーシックインカムを掲げていません。
そのために、既存政党への政策転換を呼びかけるか、ベーシックインカム導入を掲げる新しい政党・政治グループの登場を待つか、期待するか。
そのために、今回の国家長期ビジョンと政治行政改革計画の提案を行い、各党の内容との違いを確認することから、地道に進めていきたい。
そういう意図によるものであることを併せてご理解頂ければと思います。
当サイトの運営は、もちろん、地道に継続しつつ、親サイト https://2050society.com との連携も強めていきます。
どうぞよろしくお願いします。

コメント ( 1 )
トラックバックは利用できません。




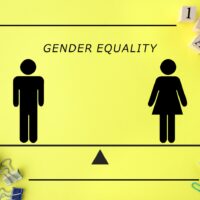









Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks