
ベーシック・インカム制導入に伴う厚生年金保険制度改革:BI導入シアン-13(2020/7/18)
今回は、BI導入とともに廃止される国民年金と関連している、厚生年金制度改革のあり方について思案する。
先に以下の記事で、子ども以外へのBI、生活基礎年金が、高齢者においては、現在の老齢基礎年金に代わるものになり、それにより自動的に国民年金制度が廃止になることを思案した。
◆ ベーシック・インカム制導入で国民年金制度は廃止へ:BI導入シアン-9
そこで、国民年金の廃止に伴い、厚生年金保険制度をどのように改定・改革するかのポイントになる部分を再度取り上げ、もう少し整理してみたい。
給与所得者全員が、新・厚生年金保険加入へ
現状、国民年金と2階建て方式になっている厚生年金では、納付した保険料の一部が、国民年金の財源に拠出されている。
国民年金廃止により、その拠出の必要がなくなり、老齢厚生年金の原資に充当できるようになる。
また、被保険者の扶養配偶者は国民年金加入の必要も負担もなかった。
新・厚生年金保険制度では、自営業者はもちろん、従来一定基準以下の所得で保険加入の必要がなかった非正規労働者、パート・アルバイト被用者など、所得がある人すべてが加入し、保険料を納付する義務を負う。
(但し、一定額以下の賃金の場合負担を免じる規定を設定することもできる。)
その保険料率は、所得税率とともに、検討されることになる。
(参考)
◆ 所得税を主財源とするベーシック・インカム制で所得税法改正へ:BI導入シアンー10
但し、私は、厚生年金保険制度単独で設定するのではなく、健康保険・介護保険・雇用保険とも統合して<社会保障保険制度>として一括した保険料率を設定することを提案したい。
(参考)
◆ ベーシック・インカム制と同時に改革・導入する社会保障保険制度:BI導入シアン-12
以下は、案ではなく、一つのイメージとして数字をはめ込んだもの。
(収入) (BI所得税率) (住民税率) (社会保障保険料率)
・ 10万円未満 5% 0% 2%
・ 10万~25万円未満 10% 2% 4%
・ 25万~50万円未満 15% 4% 6%
・ 50万~100万円未満 20% 6% 8%
・100万~ 250万円未満 25% 8% 10%
・250万以上 30% 8% 12%
全事業所・事業主が、新・厚生年金保険に加入
給与所得がある者全員が、新・厚生年金保険に加入する。
これは、その給与を支払う事業所・事業主が、保険料を控除する事務を行う義務があることを意味する。
従来は、業種や事業規模により、加入する義務がなかった非適用事業所や任意適用事業所も、すべて強制適用事業所になるわけだ。
それまで国民年金に加入するしかなかった自営業者は、新しい厚生年金保険に加入することになる。
この場合、雇用者負担をどうするか。
こうした事業主負担については、後述するが、新制度設計において、賦課方式のままで行くか積立方式に変えるか、雇用保険をどう改革するかなど、他の制度と総合的に勘案して方針と詳細を決めるべきであり、時間をかけたい。
世代間の不公平感をなくすべく、賦課方式から積立方式に
現在の年金制度は、賦課方式とされ、現役世代が、年金受給高齢世代を支える方式である。
これによる現役世代の不満・不安を抑止するものとして、BI、生活基礎年金制度は大きく寄与する。
だが、現役世代が高齢になった時に備える、生活基礎年金に上乗せする厚生年金制度は欠かせない。
そのために賦課方式を存続させるのでは矛盾がある。
従い、賦課方式から、所得に応じて料率を設定した保険料を積立て、その積立実績に応じた保険給付を、一定年齢以上で自分の希望する年齢から受け取る方式に改定する。
積立方式へ転換することが望ましいだろう。
企業(雇用者)負担をどうするか
現状、被保険者が納付する額と同額、雇用者が負担する法定福利費としての保険料。
積立方式に転換した場合、従来どおり雇用者も同じように負担する方式を維持するかどうか
前回は、その負担を廃止することが望ましいと述べたが、完全廃止ではなく、負担率を下げる方向で考えたい。
従来厚生年金保険に加入を義務付けられていなかった非正規被用者など、すべての有所得者が、新制度に加入する方式を提案しているためである。
部分的には、企業サイドの負担は減るが、社会保障制度全体の改定も必要であり、<社会保障保険制度>としての包括的な保険料率設定の中で考えたい。
またBI導入に伴い行なう所得税改定と繋がる税制改革における法人税制改定にも関連させて検討・決定を要するためでもある。
新制度移導入に伴う調整事項と対応思案
現状制度の3つの老齢・障害者・遺族厚生年金とその基本措置
現状の厚生年金制度は、
1.老齢厚生年金 2.障害者厚生年金 3.遺族厚生年金
の3種類で構成されている。
そのいずれの被保険者にも、BIである生活基礎年金が支給されるので、当然、それぞれの厚生年金の受給方法や金額も変更されることになる。
例えば、現状の老齢厚生年金受給者への家族加算である加給年金は支給されなくなる。
ただ、3年金とも、新・厚生年金保険制度で決められた老齢厚生年金に基づいて支給額(年金及び手当金)が支給されることになると現状しておきたい。
無所得者の年金無加入も
国民皆保険制がわが国の特徴であるが、年金制度に関しては、BIによる生活基礎年金制度は、保険料を財源とするものではないため、新・厚生年金保険に加入しない住民は、保険適用された者ではなくなる。
現状でも、20歳未満で所得がない者は、どの年金にも加入していない。
しかし、20歳以上の学生や被扶養配偶者は国民年金強制加入者だ。
その学生や配偶者がまったく収入がなければ、新・厚生年金保険に加入しないので、年金保険無加入者ということになる。
だが児童基礎年金か生活基礎年金を受け取るので、年金保険無加入だが年金受給者ではある。
厚生年金被保険者配偶者の離婚時年金分割制度の適用
年金保険料負担の必要がなかった被扶養配偶者が、離婚時に、配偶者が負担してきた保険料を2分の1等に按分する、<合意分割制度>や<3号分割制度>が現制度にある。
新・制度への移行に際しては、この分割制度にならって、それまでの保険料積立分を分割することになるだろう。
この他にも、当然、新・厚生年金保険制度が改定・導入される際には、多くの調整が必要になる。
当然、極力問題の発生を最小限にできる制度改革を目指したいが、簡単でないことは想像できる。
これからの検討・準備作業を通じての意義ある取り組みになる。
ここまで、BI導入に関連して、国民年金制度、所得税、社会保障制度、厚生年金保険制度などのあり方について思案してきた。
これ以外に、税制全般との関係、医療保険・介護保険との関係、新しい雇用保険(私は就労保険または就業保険をイメージしている)のあり方などについては、いずれ思案対象とし、投稿したいと考えている。
次回は、BIとして支給されるお金の管理と運用方法について思案したい。

-----------------------------
本稿は、WEBサイト https://2050society.com 2020年7月18日投稿記事 2050society.com/?p=903 を転載したものです。
当ベーシックインカム、ベーシック・ペンション専用サイト http://basicpension.jp は2021年1月1日に開設しました。
しかし、2020年から上記WEBサイトで、ベーシックインカムに関する考察と記事投稿を行っていました。
そこで、同年中のベーシックインカム及び同年12月から用い始めたベーシック・ペンションに関するすべての記事を、当サイトに、実際の投稿日扱いで、2023年3月から転載作業を開始。
数日間かけて、不要部分の削除を含め一部修正を加えて、転載と公開を行うこととしました。
なお、現記事中には相当数の画像を挿入していますが、当転載記事では、必要な資料画像のみそのまま活用し、他は削除しています。
原記事は、上記リンクから確認頂けます。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。







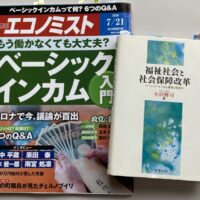






この記事へのコメントはありません。