
ベーシックアセットとは?:ベーシックアセット提案の宮本太郎氏のベーシックインカム論-2
宮本太郎氏著『貧困・介護・育児の政治 ベーシックアセットの福祉国家へ』(2021/4/9刊) を参考に、社会保障政策視点からは、親Webサイト https://2050socitey.com で、ベーシックインカムの観点からは当サイトで、シリーズ化して投稿を始めています。
初めに、当サイトで以下を。
◆ ベーシックアセット提案の宮本太郎氏のベーシックインカム論-1(2021/8/20)
次に、2050society で以下を。
◆ 福祉資本主義の3つの政治的対立概念を考える:宮本太郎氏『貧困・介護・育児の政治』序論から(2021/9/2)
そして今回は、双方を受ける形で、同書のサブタイトルにある「ベーシックアセット」論について具体的に確認することにします。
ベーシックアセットの、ベーシックインカム、ベーシックサービスとの違い
まず簡単に宮本氏は、ベーシックインカム、ベーシックサービス、ベーシックアセットの違いをこう示します。
1)ベーシックインカム:すべての市民に同額の現金給付するもの
2)ベーシックサービス:すべての人々が、その負担応力の如何に依らず、ニーズを満たす上で基本的で十分に受けとることができる公共サービスで、医療、教育、ケア、住宅、輸送、デジタル情報へのアクセスなどを包括する。
3)ベーシックアセット:現金給付、サービス給付にコモンズを加えたもの
コモンズとは何か? それが分からない限り、肝心のベーシックアセットとは一体何なのか・・・。
アセットとは? コモンズというアセットとは? その前にコモンズとは?
まず本書とは切り話して、会計学的な「アセット」の意味は「資産」。
広義には、政府・企業・家計など経済主体に帰属する金銭・土地・建物・証券などの経済的価値の総称とされます。
次に本書におけるアセットとは。
広くは、ひとかたまりの有益な資源という意味であり、現金給付も公共サービスもアセット。
そして、
1)ベーシックインカムは、私的アセットを現金給付で
2)ベーシックサービスは、国と自治体の公共アセットを、サービス給付で
3)ベーシックアセットは、私的・公共的アセットに、コモンズのアセットを加える
とし、こう続けます。
コモンズというアセットとは、
誰のものでもなく、オープンで、多くの人がその存続に関わるが、その分、誰かが占有してしまう場合もあるようなアセットで、コミュニティ、自然環境、デジタルネットワーク等がそれに当たる。
同書との関係で重要なコモンズのアセットは、社会と繋がり続け、承認を得ることができるコミュニティというコモンズであると。
ところで、コモンズとはなにか、です。
不思議なことに(見逃しているのかもしれませんが)、本書の序論で宮本氏はコモンとコモンズについて、定義的にはほとんど説明しておらず、コモンズのアセットとしてコミュニティ、自然環境、デジタルネットワークを挙げているだけです。

そこで、唐突ですが、以前当サイトで取り上げた斉藤幸平氏によるベストセラー 『人新世の「資本論」 』(2020/9/22刊) の <第6章 欠乏の資本主義、潤沢なコミュニズム> の中で、コモンとコモンズについて課題としていましたので、その一部を参考にしたいと思います。
『人新世の「資本論」』におけるコモンとコモンズ
が、残念なことに、その<第6章 欠乏の資本主義、潤沢なコミュニズム> を対象とした以下の記事内で、コモンとコモンズについてあまり触れていませんでした。
◆ 資本主義と左派加速主義批判の後に来る脱成長コミュニズム:『人新世の「資本論」 』が描く気候変動・環境危機と政治と経済-3(2021/4/29)
そこで、同記事にも挿入した同章を構成する小見出し中に2つの用語が組み込まれていたので、以下にピックアップしました。
・コモンズの解体が資本主義を離陸させた
・水力という<コモン>から独占的な化石資本へ
・コモンズは潤沢であった
・「コモンズの悲劇」ではなく「商品の悲劇」
・<コモン>を取り戻すのがコミュニズム
・<コモン>の「<市民>営化」
・ワーカーズ・コープ ー 生産手段を<コモン>に
これらからのイメージを持ちつつ、そこでの文章から一部を借用してみます。
土地は根源的な生産手段であり、それは個人が自由に売買できる私的な所有物ではなく、社会全体で管理するものだったのだ。だから、入会地のような共有地は、イギリスでは「コモンズ」と呼ばれてきた。
(略)囲い込みによって、このコモンズは徹底的に解体され、排他的な私的所有に転換されなければならなかった。
(略)
土地だけではない。資本主義の離陸には、河川というコモンズから人々を引きはがすことも重要であった。(略)
水力は自然に潤沢に存在しており、完璧に持続可能で廉価な動力源だった。共同で管理可能な<コモン>だったのである。
ここでもしっかりした定義は見られないのですが、この内容で、イメージを持つことはできます。
宇沢弘文氏の「社会的共通資本」でイメージするコモンとコモンズ
そこでもう一つ、当サイトで以前取り上げた、宇沢弘文氏の 『社会的共通資本』 の3分類を紹介します。
1.自然環境:大気、水、森林、河川、湖沼、海洋、沿岸湿地帯、土壌など
2.社会的インフラストラクチャー:道路、交通機関、上下水道、電力・ガスなど(社会資本ともいう)
3.制度資本:教育、医療、金融、司法、行政などの制度
どうでしょうか、
<自然環境>と<社会的インフラストラクチャー>。
前者がコモンズ、後者がコモンと捉えることができるかもしれません。
コモンとコモンズはここではこのくらいにしておきましょう。
宮本氏の書の最終章で、ご本人によるコモンとコモンズの説明を期待したいと思います。
しかしただ単純に、複数形のsが付くか付かないかの使い分けなのかもしれません。
そして、コモンズを価値・資産と見ればアセットとみなす。
資産価値、人々にとって有用であるならば、コモンもしくはコモンズ。
その程度の軽い気持ちで漠然と把握していればよいのかもしれません。
サービスと現金給付のアセットとアセットの最適性
宮本氏の表現にあった「誰のものでもないが、誰かが占有してしまう場合もあるようなアセット」。
サービス給付、現金給付、コモンズ(例えば帰属するコミュニティ)は、市民に一律に配られるギフトパッケージのように既に詰め合わせになっているわけではない、とも言っています。
その内容は一人ひとりの市民の抱えている生きがたさや困難によって異なってくる。
このアセットの複合性と共に、人々にとっての最適性が、ベーシックアセット論の大きな可能性である。
この辺りは、何やらベーシックサービスと似通っています。
こうした曖昧さを払拭するため、ベーシックアセットを理解するためには、3つの観点から視点を変える必要があるとします。

ベーシックアセット理解のために必要な3つの視点転換
その3つの視点とは、
1)コモンズというアセットの理解
2)「再分配」から「当初分配」へ
3)最適なアセットの組み合わせ
であると。
そこで再度、コモンズというアセットの理解を試みるために、同氏の提案事例を見ることにします。
デジタル課税や環境課税による社会保障財源確保につながるコモンズというアセット
1つ目の視点転換は、コモンズというアセットを視野・前提とすること。
具体例を示すと、デジタルネットワークというコモンズ。
すべての利用者が存在・参加して成立するコモンズだが、巨大ITビジネス・プラットフォーマーだけが手にする莫大な利益にデジタル税を課すことで、それらを資源とみなすことができ、実際に社会保障財源とすることができる。
あるいは、自然環境というコモンズにおいては、その私的利益のために浪費され環境悪化をもたらすことに対して環境税を課し、同様に財源化する。
コモンズが、財源・資源すなわちアセットに転換される。
なるほど、これで合点がいく内容が示されました。
ただそれらが無条件に、すんなりと受け入れられ、導入・実現されるかどうかは定かではありませんが。

社会保障給付を「事後的補償から事前的予防へ」、「再分配」から「当初分配」へ
2つ目の視点転換は、社会保障給付を事後的な再分配より、人々の社会参加を可能にする事前の資源(アセット)と位置づけること、と提起します。
言い換えると、「事後的補償から事前的予防へ」となり、米政治学者ハッカーのいう「再分配」から「当初分配」という考え方になります。
この「当初分配」というコンセプト、考え方は良いですね。
当サイト提案のベーシック・ペンションも、当初分配方式です。

最適なアセットを組み合わせるとは
最後の視点転換の命題は、最適化。
その意味は、ベーシックサービスとも共通しますが、こうしたコモンズというアセットを活用できる条件が、障害の有無・度合い、ジェンダー、世代・年齢、物的環境や社会条件などで大きく異なることがベースにあります。
そこでは、給付の共通性とその基準を示すこと、見出すことは難しいですね。
だから個々に、個別に最適な組み合わせが必要ということになるわけですが・・・。
序論における考察なので、一旦ここで終わり、詳細は最終章で。
そう言われればそう受け止めるしかなく、お楽しみはとっておくことにしましょう。
なお序論と最終章以外では、ほとんどベーシックアセットについて詳しく述べられていません。
但し、ベーシックインカムについての同氏の詳論は、<第2章 貧困政治 なぜ制度は対応できないか>で展開されていますので、そこで再度触れたいと思います。
そして、当然、本稿は、ベーシックアセット自体についての序論であり、貧困・介護・育児の政治論を展開した後の最終章< 第5章 ベーシックアセットの保障へ> で全体の総括・まとめを完成させることになります。

ベーシック・ペンションとベーシックアセットとの違いの概略
総括としての第5章でのベーシックアセットに関する結論を確認した後、当サイト提案のベーシック・ペンションとの違いを確認しますが、一応、ここでその概略を書き添えておきたいと思います。
ベーシック・ペンションは
1)一応現金給付方式だが、ベーシック・ペンションの運用管理だけのための専用デジタル通貨(JBPC)を支給する。(疑似現金給付)
2)専用デジタル通貨給付に伴い、社会保障制度全体の見直し、個別制度・法律の改廃を行う。
3)サービス給付は、それらの新しい関連制度に基づき行われる。
4)その財源資源は、私的財源ではなく公的財源とするが、税・社会保障一体制とは異にする、ベーシック・ペンション自体をコモンズと称することが可能なアセットである。
5)ベーシックサービス及びベーシックアセットで明確に示されていない(示すことが困難な)財源・財政規律に対して、ベーシック・ペンションの導入に伴い、その後の社会保障・社会福祉財源は、税と社会保障一体主義、財政規律主義に則っての運用となる。
本書のシリーズ、次回は、<第1章 「新しい生活困難層」と福祉政治>をテーマに、親サイト https://2050society.com に掲載します。

コメント ( 1 )
トラックバックは利用できません。





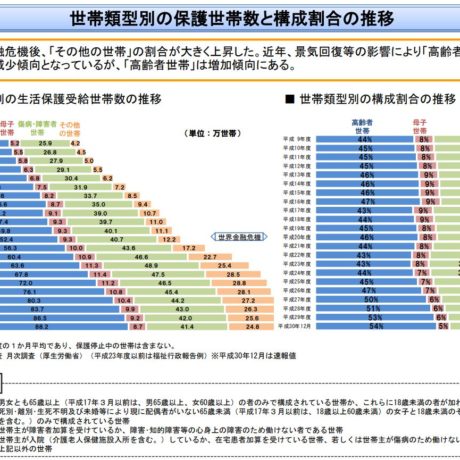








Hello are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!