
貧困政治とベーシックインカム、ベーシックアセット:ベーシックアセット提案の宮本太郎氏のベーシックインカム論-3
宮本太郎氏著『貧困・介護・育児の政治 ベーシックアセットの福祉国家へ』(2021/4/9刊) を参考に、社会保障政策視点からは、親Webサイト https://2050socitey.com で、ベーシックインカムの観点からは当サイトで、シリーズ化して投稿を進めています。
これまで当サイトでは以下を。
◆ ベーシックアセット提案の宮本太郎氏のベーシックインカム論-1(2021/8/20)
◆ ベーシックアセットとは?:ベーシックアセット提案の宮本太郎氏のベーシックインカム論-2(2021/9/4)
親サイトに当たる2050society で以下を。
◆ 福祉資本主義の3つの政治的対立概念を考える:宮本太郎氏『貧困・介護・育児の政治』序論から(2021/8/30)
◆ 増加・拡大する「新しい生活困難層」:宮本太郎氏『貧困・介護・育児の政治』からー2 (2021/9/2)
◆ 貧困政治での生活保護制度と困窮者自立支援制度の取り扱いに疑問:宮本太郎氏『貧困・介護・育児の政治』からー3(2021/9/7)
そして今回は、
◆ 貧困政治での生活保護制度と困窮者自立支援制度の取り扱いに疑問:宮本太郎氏『貧困・介護・育児の政治』からー3
を引き継ぐ形で、 <第2章 貧困政治 なぜ対応できないか>のなかでのベーシックインカムとベーシックアセットの関する部分に着目して、宮本氏の考えを確認します。
(参考):<第2章 貧困政治 なぜ対応できないか> の構成
1.生活保障の揺らぎと分断の構図
・トリクルダウンはもう起きない
・もはや頼れない家族とコミュニティ
・空転する社会保障
・分断の構造
・分断と不信の相互作用
2.貧困政治の対立軸
・貧困政治の選択肢
・新自由主義における就労義務化
・「第三の道」の就労支援
・北欧型福祉と社会的投資
・ベーシックインカムの台頭
・ ベーシックインカムの機能を決めるもの
・4つの選択肢と3つの立場
3.日本の貧困政治と対立軸の形成
・福祉政治のパターン
・新自由主義の出現
・対抗軸の形成
・中曽根改革・小泉改革と「三重構造」
・ ワークフェアの空回り
・「磁力としての新自由主義」とは何か
4.「社会保障・税一体改革」と貧困政治
・ 民主党政権とベーシックインカム型生活保障
・ 「社会保障・税一体改革」 の始まり
・ 民主党政権と一体改革
・一体改革と貧困政治
・一体改革と信頼醸成の困難
・自民党の生保プロジェクトチーム
・生活困窮者自立支援制度
・社会的投資の新しい可能性
・ベーシックアセットの保障へ
貧困政治の選択肢としての4つの対立構図とベーシックインカムの台頭
こう題した先述記事において、
生活保障政策における投入資源を、<支援型サービス給付の強弱>と<所得保障(現金給付)による所得水準の高低>の組み合わせとしたとき、
1)新自由主義(弱低) 2)北欧型福祉(強高) 3)第三の道(強低) と並んで、4)ベーシックインカム(弱高)を加え、この4つのいずれかが選択されるという宮本氏の考えを紹介しました。
では、宮本氏の想定する<ベーシックインカム>とはどういうものでしょうか。
初めに、BIEN(ベーシックインカム地球(or世界)ネットワーク)の以下の定義を紹介します。
ベーシックインカムは、所得調査を課したり、就労を求めたりすることなく、無条件に、すべての個人を対象として、定期的に行われる現金給付である。
(参考)
⇒ ベーシック・インカム世界ネットワーク(BIEN)の位置付け(2021/3/22)
すなわち、就労支援を重視する<社会的投資>とは対照的で、就労や所得状況とはまったく切り離した制度です。

ベーシックインカムの機能とその評価
そして、こんな断言を同氏はしています。
ベーシックインカムを唱える論者は、ほとんどの場合、生活保障・失業手当、児童手当、年金などの現金給付をこれに一本化し、所得の如何を問わず無条件で給付することを求める。
しかし、これは極めて一面的で、乱暴な括り方です。
どちらかというと右派、新自由主義的立場でベーシックインカムの導入を主張する人の考え方と言え、これと異なる意見、ベーシックインカム論を展開している、いわゆるリベラル系の人々も多々います。
当サイトは、そのどちらにも属さない、異なる理念に基づく提案者です。
そして、同氏は、いくつかの現金給付社会保障・福祉を一本化することに、次のような理由から一定の合理性があると言います。
自治体の生活保護のケースワークに相当の人員を割いていること、社会保険制度に相当の行政コストがかかるこ年金機構が所管する複雑膨大な年金管理業務など、ベーシックインカムの導入で、それらの行政経費が不要になり、他の給付に回すことができ、生活保障制度の透明度も増す。
その一方で、以下を懸念します。
国の特定の制度に人々の生活が根本から左右されるのは、たいへん危うく、各種の所得保障を一本化してベーシックインカムが導入され、後にその給付が引き下げられたりすれば打撃は甚大である。
まあ、このレベルの不安を指摘することになれば、ベーシックインカムにとどまらず、すべての政治にリスクが存することを問題としなければならなくなり、例え話としては不適であることは明らかです。
要するに、同氏が、ベーシックインカムの給付額や既存制度をどうするか、財源をどうするかによって、その効果が大きく異なることはもちろん、それらの違いは、元来、ベーシックインカム導入の目的・方針の違いに存するものです。
従い、ベーシックインカム論を考察・評価する上では、部分のみの提案は評価の対象とすべきではないと私は考えています。
そういう点で、これまでのところの宮本氏の説は、十分な内容・レベルの記述は見ておらず、まだ「論」と呼ぶには至らないとみています。

小沢修司氏と原田泰氏のベーシックインカム提案とその比較
本節において、宮本氏は、小沢修司氏と原田泰氏両氏のベーシックインカム提案を紹介し、若干の比較を記しており、以下に整理してみました。
なお、小沢氏は、日本におけるベーシックインカム論の古典と言える『福祉社会と社会保障改革―ベーシック・インカム構想の新地平』を2002年に発刊。
原田氏は、やはりBI論のテキストの1冊とされている2015年刊の『ベーシック・インカム 国家は貧困問題を解決できるか』を書き表しています。
小沢修司氏のベーシックインカム
・<支給額>:すべての市民に月額8万円支給、両親・子ども2人世帯年間給付額は384万円
・<基本方針>:① 社会保障の現金給付部分をBIで置き換える
② 介護・保育・医療などのサービス給付は削減しない
・<税制>:税控除を全廃し、所得税を一律50%に引き上げ、財源に。
・<その影響>:年収700万円までの世帯はBI導入で、再分配後の所得が増大する
原田 泰氏のベーシック・インカム
・<支給額>:すべての大人月額7万円、子ども同3万円支給、同年間240万円
・<基本方針>:① 社会保障の現金給付部分をBIで置き換える
② 公共事業予算・中小企業対策費・農業予算等の一部を財源に
・<税制>:所得控除を廃止し、所得税を一律30%にし、財源に。
・<その影響>:中所得者にとり現行制度による負担と給付があまり変わらない
高所得者の所得税負担は軽減される
(参考)
⇒ リフレ派原田泰氏2015年提案ベーシックインカム給付額と財源試算:月額7万円、年間総額96兆3千億円 (2021/2/3)
上記で見られる両氏提案の構想の差の大きさについて、原田氏が小沢氏との議論の違いを「イデオロギーの問題」としていることを取り上げ、宮本氏は、原田論は経済的自由主義の性格が強く、小沢論は、より社会民主主義的としています。
しかし、原田氏が、介護・保育・医療などのサービス給付をどうするかは、実は明確に述べていません。
ただ、高所得者の所得税負担が軽減されるということについては、同氏が今は考え方を変えるべきと思っていることを期待したいところです。
小沢氏の提案・主張内容は、まだ前掲書を手にしておらず、確認していないので何とも言えませんが、書のタイトルから想像すれば、社会民主主義的立場での提案だろうと推察します。
この記事に取り組みがてら、Amazon で適切な中古書がないか確認したところ、運良くあったので注文しました。
確認後、報告がてら紹介したいと思います。
貧困政治における4つの選択肢の1つとしてのベーシックインカムの中での選択肢
私自身は、「北欧型福祉」「第三の道」「新自由主義」及び「ベーシックインカム」のいずれも、これからの日本の社会保障・福祉制度の選択肢とすべきとは思っていません。
宮本氏は、ここでは、以下の確認で終えています。
しばしば一つの制度であるかのように論じられるBIも、累進的は所得税で財源を調達し、高い水準のBIを導入するか、現行の税制の枠内で(あるいは減税をして)、経済支援の制度全般を一本化して財源を調達しつ導入するかで、まったく別物となる。
社会民主主義的BIか、新自由主義的BIかという違いである。
加えて保守主義的なBIも考えられる。
その導入のために保育サービスなどの財源が犠牲になり、給付が世帯主の口座に振り込まれ、女性が家庭で家事や育児を担うことの報償のような意味をもてば、ジェンダー分業を固定化させる結果になるからである。
随分暗い例え話を最後に持ってきましたね。
悪い冗談、悪い寓話と無視するわけにはいきませんが、それぞれのどこかに共通点があり、突き詰めていけば、すべてを包摂するセーフティネットとして、そしてよりベーシックな意味での基本的人権としてのベーシックインカムを統合できると考えています。
その一つのヒントになり、選択肢にもなりうるのが、当サイト提案のベーシック・ペンションなのですが、その前に、宮本氏提案のベーシックアセットを深く考える必要があります。
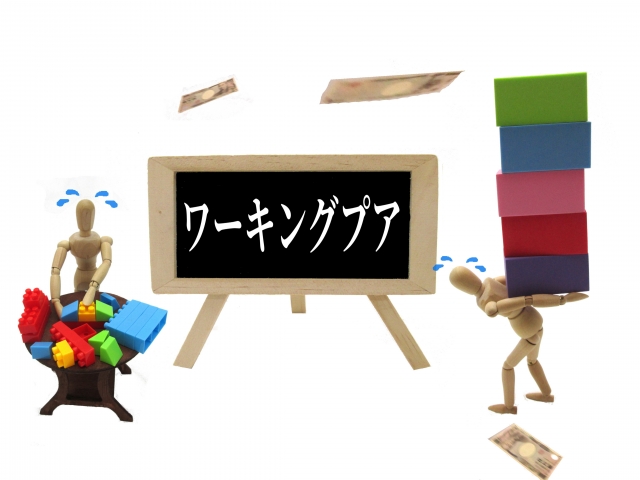
社会的資本としてのベーシックアセットという考え
本章の最後の節のタイトルは、<ベーシックアセットの保障へ>。
同氏提案のベーシックアセットの基本的な知識は、先の以下の記事で本書の「序」から紹介しました。
◆ ベーシックアセットとは?:ベーシックアセット提案の宮本太郎氏のベーシックインカム論-2(2021/9/4)
一部を繰り返すと
ベーシックアセット(BA)とは、ベーシックインカム(BI)とベーシックサービス(BS)との対比で打ち出した議論。
BIのような私的アセット、BSが強調する公的(行政的)アセットに加えて、コモンズのアセット(参加可能なコミュニティ等)を含めて、人々が社会に参加していくのに必要なアセットの組み合わせを提供する、という考え方
BIは同額の現金給付を、BSは同水準の行政サービスの提供を普遍性の基準とし、制度が公正である根拠とする。
これに対して、BAは、人々を各自が力を発揮できるために必要な最適のアセットとつなぐ、というところにポイントがある。
最適のアセットに繋ぐ方法について、サービス給付については包括的相談支援が重要に。
更に、準市場の制度を洗練させていくこともサービスのアセットにつなぐ制度である。
現金給付については、BIのように均一給付にこだわらないとし、選別的制度として、給付対象の「的を絞る」ターゲティングの方法を納得感が高いものにしていくという考え方も添えています。
同様の考え方・手法で、住宅手当や子どもの貧困率抑制に直結する給付によるBAも事例として挙げ、BAを推奨する根拠として、本章を終えています。
まだまだ、突っ込みが浅い論述と感じます。
最も気になるのは、やはり、運用上の共通の基準を果たして示すことができるか、です。
得てして、社会民主主義的なBI論、そしてBS論では、結局基準を設定するレベルになかなか到達できないのです。
そこに、暴力的な、新自由主義的BIが入り込むことができるスキを与えてしまう側面があると感じています。
当サイト提案のベーシック・ペンション生活基礎年金と貧困政治との関係
しかし、だからといって、当サイト提案の日本独自のベーシックインカム(BI)、ベーシック・ペンション(BP)は、細かい基準を設定することに注力し、拘泥するわけではありません。
むしろ、BP自体は、運用上の要件・基準は簡単にして、関連する幾つかの社会保障制度も、基準を必要なくす、あるいは簡単にすることをめざすもの。
そして、他の社会保険・労働保険を含め、社会保障制度についても極力、分かりやすい基準・規定のものに改正する。
その方針・方向を目指しています。
それが、貧困政治自体を分かりやすく、利用しやすくすることに繋がると考えるのです。
ということで、宮本氏提案のベーシックアセットの総括と評価は、同書の最終章<第5章 ベーシックアセットの保障へ>に到達してから行うこととしたいと思います。

(参考)ベーシックサービス関連記事リスト
1.今野晴貴氏「労働の視点から見たベーシックインカム論」への対論
(2020/11/3)
2.藤田孝典氏「貧困問題とベーシックインカム」への対論(2020/11/5)
3.竹信三恵子氏「ベーシックインカムはジェンダー平等の切り札か」への対論(2020/11/7)
4.井手英策氏「財政とベーシックインカム」への対論(2020/11/9)
5.森 周子氏「ベーシックインカムと制度・政策」への対論(2020/11/11)
6.志賀信夫氏「ベーシックインカムと自由」への対論(2020/11/13)
7.佐々木隆治氏「ベーシックインカムと資本主義システム」ヘの対論(2020/11/15)
8.井手英策氏「ベーシック・サービスの提唱」への対論:『未来の再建』から(2020/11/17)
9.井手英策氏「未来の再建のためのベーシック・サービス」とは:『未来の再建』より-2(2020/11/18)
10.ベーシックサービスは、ベーシックインカムの後で:『幸福の財政論』的BSへの決別と協働への道筋(2020/11/26)
(参考):ベーシック・ペンションの基礎知識としてのお奨め5記事
◆ 日本独自のベーシック・インカム、ベーシック・ペンションとは(2021/1/17)
◆ 諸説入り乱れるBI論の「財源の罠」から解き放つベーシック・ペンション:ベーシック・ペンション10のなぜ?-4、5(2021/1/23)
◆ 生活基礎年金法(ベーシック・ペンション法)前文(案)(2021/5/20)
◆ 生活基礎年金法(ベーシック・ペンション法)2021年第一次法案・試案(2021/3/2)
◆ ベーシック・ペンションの年間給付額203兆1200億円:インフレリスク対策検討へ(2021/4/11)

コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。







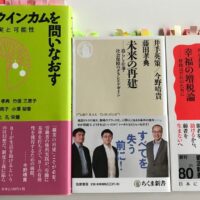






この記事へのコメントはありません。