
18世紀末、2人のトマス、トマス・ペイン、トマス・スペンスの思想:ベーシックインカム構想の起源
今回は、日本のベーシックインカム研究の第一人者のひとり、山森亮氏に拠る『ベーシック・インカム入門 』(2009/2/20刊)から引用させて頂きます。
トマス・ペインの思想
同氏によると、ベーシック・インカム構想の出現は18世紀末。
その証拠・記録として提示しているのが、イングランドの思想家トマス・ペイン(イングランド出身・米国の哲学者:1737~1809)の書『人間の権利』。
フランス革命やアメリカの独立戦争にも参加している彼の同書には、現在でいう年金や生活保護に当たる話があり、「それは慈善の性質をもつものでなく、権利に属するものである」としています。
そして『土地配分の正義』(1796年)というパンフレットにある
「21歳になったら15ポンドを成人として生きていくための元手として国から給付されるべき。50歳になったら10ポンドを年金として受け取る。」
という内容を紹介します。
これは、生活のためでなく、事業のためということで、ベーシック・インカムでなく、ベーシック・キャピタルと呼ぶこともあるそうです。
そしてまた、以下のように土地の所有権やそれを巡る不正義を論じます。
本来人類の共有財産だった土地の私有化という不正義により貧困が生まれた。
ゆえに、その補償として土地所有者に課税し、その税金で皆が食べられるよ
うにすべきである。
しかし、トマス・ペインは、こうしたベーシックインカム等の福祉構想よりも、先述した活動家として記憶されており、アメリカ独立戦争最中、アメリカ植民者を奮い立たせるためにその地で書いた『コモン・センス』(1776年著)の方が知られていることも山森氏は紹介しています。

トマス・スペンスの思想
次に、ほぼ同時代のイングランド哲学者トマス・スペンス(1750~ 1814)が、トマス・ペインの『人間の権利』の批判書として書き表した『幼児の権利』にある以下の主張が、ベーシックインカムを指すと言います。
土地はイングランドの地域共同体の単位、教区ごとに共有し、土地を居住・
農耕などの目的で専有する場合、教区に唯一の税金としての地代を払う。
ここから公務員給与など共同体の必要経費が支出された後の剰余金を、男女、
既婚・未婚、嫡出・非嫡出等を問わず、年4回、成員に平等に分配されるべ
き。
そして、スペンスのこのベーシックインカム案は、「スペンソニア」や「スペンスの計画」と呼ばれる包括的な社会改革案の一部であり、最古のベーシック・インカム提案と山森氏は述べています。
フランス革命は、イングランド自国の危機ではなかったにも拘らず、トマス・ペインやトマス・スペンスが母国からなぜ迫害・弾圧を受けたのか。
それは、そうした急進的な思想が、自国に伝搬し、影響を受けることを恐れたため、というのも合点がいくところです。

18世紀~19世紀初頭の欧米の歴史的背景と現在のベーシックインカム論
二人のトマスに共通の自然権思想は、ベーシックインカム論用だけに限定されることなく、歴史的定説の一つとして語られます。
しかし、この後のトマス・スペンスの思想も同様ですが、当時のキリスト教および王政・貴族制社会においては、当然異端とされ、書の発禁処分はもとより逮捕・投獄されるなど不遇をかこつた時代・社会であったことを知っておく必要があります。
というのは、その時代が、アメリカ独立戦争(1775~ 1783)やフランス革命(1789~ 1799)など、宗教的にも貴族を含む王政上も、その権威が脅かされ、時代が大きく変わろうとす狭間にあったのです。
そして200数十年を経た現在においても、ベーシックインカムを論じる上で、こうした異なる思想観に拠り、異なる考え方を戦わさなければいけない課題として抱えていることを、私たちはどう評価すべきでしょうか。
2つの世界大戦を経てもなお、でもあります。
ベーシックインカムをどうするか。
近世・近代を遥か過去のものとし、現代もすでに何世代かを継承し、それぞれの国とグローバル社会の時空間を共有しつつ向かう未来に向かって、もうそろそろ望ましいありかたを具現化しても良いのでは、と思うのですが。
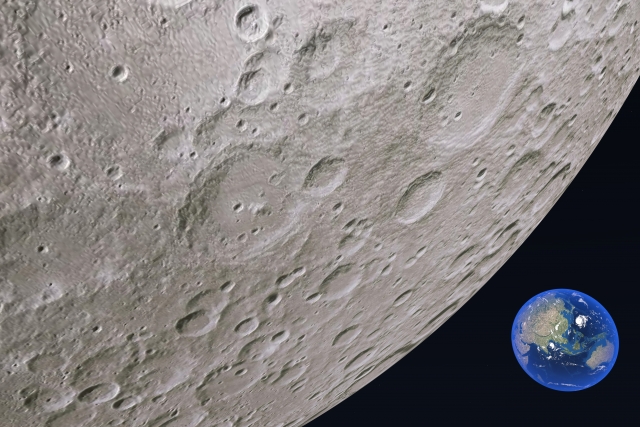
こちらも関連して確認頂きたい記事です。
◆ イギリス救貧法の歴史・背景、概要とベーシックインカム:貧困対策としてのベーシックインカムを考えるヒントとして(2021/1/26)
◆ ミルトン・フリードマンの「負の所得税」論とベーシックインカム(2021/2/19)
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。


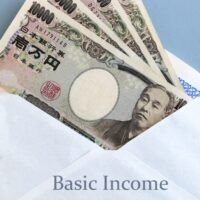
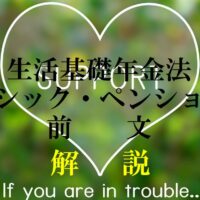



















この記事へのコメントはありません。