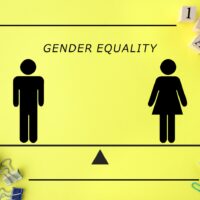佐々木隆治氏「ベーシックインカムと資本主義システム」ヘの対論(2020/11/15)
『ベーシックインカムを問いなおす: その現実と可能性』対論シリーズ-7
『ベーシックインカムを問いなおす その現実と可能性』(法律文化社・2019/10/20刊)
を用い、同書で問い直すべきとしているベーシックインカムについての各章を対象として、私が考え提起する日本型ベーシックインカム生活基礎年金制と突き合わせをするシリーズを進めてきました。
第1回:今野晴貴氏「労働の視点から見たベーシックインカム論」への対論(2020/11/3)
第2回:藤田孝典氏「貧困問題とベーシックインカム」への対論(2020/11/5)
第3回:竹信三恵子氏「ベーシックインカムはジェンダー平等の切り札か」への対論(2020/11/7)
第4回:井手英策氏「財政とベーシックインカム」への対論(2020/11/9)
第5回:森 周子氏「ベーシックインカムと制度・政策」への対論(2020/11/11)
第6回:志賀信夫氏「ベーシックインカムと自由」への対論(2020/11/13)
今回は、第7回目で、佐々木隆治氏による<第11章 ベーシックインカムと自由>を題材にしての対論です。
佐々木隆治氏の本論の視点
タイトルどおり、BIと資本主義システムとの関係についての小論ですが、基本は、資本主義システムにおいて導入するBIは、成立・機能しないという見方を展開するものです。
前回の志賀氏の議論の基調と同じですから、正直あまり真剣に取り合う気持ちになれないのですが、むしろ次回、『未来の再建』の中での井手英策氏のBSベーシッサービス具体論に繋ぐ意味合いで、と思います。
また、本書のまとめに当たる部分でもありますし。
権力性を持つ貨幣論、その意味・意義とは?
初めの節で、<市場と貨幣の権力性>というテーマで、資本主義市場において貨幣がもつ権力性について記述しています。
資本主義システムにおいては、貨幣は「直接的交換可能性」という特別な力を持った物象であり、貨幣さえあれば、個人は人格的関係に依存することなく社会的力を行使し、他者を動かすことができるし、自らが望むときにいつでもその力を行使できる。
要は、貨幣は、危険なモノ、存在であるということです。
貨幣をそう捉えると、確かにそういう側面はあるかもしれません。
が、それだけではない、ということ、それ以外の大きな機能や可能性も持っていることを捨象して、BI批判に結びつけるのは、早計であり、教条主義的と言うべきでしょう。
まあ、BS論者は、BIの機能・可能性を認めはするが、それよりもBSが優る、という伝道者の立ち位置ですから、やむを得ないですが。
何より、貨幣は、一党独裁共産主義体制においても、十二分に権力性を持っていることも確認しておきましょう。
ベーシックインカムと資本主義社会
そして、資本主義システム社会におけるBI批判に向かいます。
<BIと市場の偶然性>という項では、市場における商品化された社会的サービスが不十分であったり、十分な貨幣を持たないことで利用できないなどの偶然性が問題とします。
では、脱商品化した社会的サービスにおいては、すべてを提供できる保障があるのでしょうか。
医療分野の現物給付制度がしっかりしていれば、必要なサービスを無料か非常に低額で受け取ることができるが、こうした現物給付がまったくなかったら、どうなるだろう。
こんな例えで、いきなり「まったくなかったら」という比較条件を持ち出してくる稚拙さにはあきれかえります。
これは、BS論者の多くに共通の特性です。
オールオアナッシング法です。
人間が生きていくなかでいろいろな物資やサービスを必要としたとき、市場の内部だけで対処するには限界がある。
これも、同様の論法です。
では、脱商品化し、社会的サービスに委ねれば、際限なく必要すべてを満たすことが可能になるのか。
BS論者は、自信をもって「可能」と言うのです。
「必要」の程度や内容・質、量については語りません。
必要を満たすために様々な必要な基盤・条件などについても、あまり気には留めていないようです。
また、こう言います。
生存を保障するにあたって最も重要なことは、人間が生きるのに最低限必要な基礎的な社会的サービス(医療、住居、教育など)を市場の論理から切り離していくことである。
すなわち、それらを普遍主義の原則に従って無償で保障することが必要となる。
井出氏の論を用いてこう表現しているのですが、真意は、この社会的サービスは、すべて公費で賄うべきということになるでしょう、というか、それしかないですね。
では、その公費の財源はなにか。
井出氏によれば、消費税を財源とすることになります。もちろん増税により、です。
しかし、その社会的サービスの前に、生きるために先ず最低限必要なのは、食費・衣類日用品費など基礎的な生活費が欠かせません。
なぜかBS論派は、そこに触れることがほとんどなく、すでにそれらは充足されていることを条件として、基礎的社会的サービスの無償提供で、めざす理想は実現できるとしているのです。
この続きは、『未来の再建』の内容・概要を確認して論じることにしましょう。
<BIと貨幣の権力性>の項では、それらの力が人間の共同性を解体する方向に作用し、人間性や社会との結びつきを根本的に変え、公的ないし地域的支援の社会的基盤が失われてしまうと言います。
加えて、ギャンブル依存症、ソシャゲ依存症、買春の蔓延など、貨幣の魔力がもたらす社会悪にも批判は及びます。
貨幣にこうした負の側面を引き起こす責任のすべてを負わせるのも極端が過ぎます。
そうならば、競馬競輪競艇などギャンブルの禁止、ゲーム開発販売の禁止、風営法の強化など先行して取り組むべきでしょう。
そうした問題の根は、商品化する人と社会にあるわけで、専ら貨幣が負うべきものではないはずです。
社会的サービスの脱商品化の前に、アディクション等問題を発生させる危険性を帯びた貨幣交換物の非商品化を主張する方が先決でしょう。
ところが、そういう話はBS論から、もちろん藤田氏の論述からも出てきません。
純粋な気持ちでBS論を主張するならば、根源的な問題にもアプローチすべきと思うのですが。
そして、<BIと賃労働>の項では、お決まりの労働と所得とを切り離すことを目的としたBI論への批判です。
そう論じるBI論者もいますが、それはBIの額によりけりの話であり、私が提案するJBI日本型ベーシックインカム生活基礎年金制は、BIにより労働を分離・分割することを目標・目的とはしていません。
生きる上で労働を主に据えるか、サブ的なものとするか、労働を回避するかは、人それぞれの選択によるものとしています。
資本主義システムとBI論とをかけ合わせると、必然的に新自由主義によるBIを反射的に想像し、ファイティングポーズを取ろうとします。
資本主義と新自由主義は確かに親和性があり、一体かのように思われます。
しかし、そこの親和性レベルと同一のものとしてBIを論じるのは、もうやめるべきでしょう。
BS派がイメージする社会は、資本主義社会か社会主義社会か
実のところ、BSが資本主義システムとどういう関係性を持つのかも、BS論では不明確なのです。
論調から類推すると、社会主義派かと思われるのですが、財政学者がBS論を牽引しているので、資本主義容認派であるとも思えます。
しかし、その内容である社会福祉の脱商品化の行き着く先は、資本主義社会ではないということになりそうです。
そのへんの曖昧さは、ずーっと払拭されないままです。
その財政学においても、中央銀行の通貨発行権に基づくBI論やMMTに依拠する財政政策の自由性を採用してのBI論など、BS論においても取り上げて欲しい、取り上げるべき課題があります。
それもほとんど無視されています。
また、個別の話になりますが、福祉国家における無料や低価格での社会福祉サービス利用は、高負担で支えられていることに触れていないのはなぜでしょう。
むしろその実際を数字を用いて説明する必要があると思うのですが、BS論にはほとんど出てきません。
これも不思議というよりも、不信感を抱かせる要素の一つと考えています。
コロナが明らかにしたBIの必要性・有効性とBSの機能不全・不十分さ
コロナで現代の貨幣システムのもとで管理される財政システムにおいて、赤字国債の大規模な発行、財政赤字の膨張も、やむを得ないものとされつつあります。
それなしにはこの長引く危機を乗り越えることはできなくなっているのです。
福祉国家においても、資本主義国家においても、です。
BIに宿る基本的な目的・機能が、特別定額給付金や持続化支援給付金の支給が行われ、再度行う必要性も喧伝されることで理解されつつあるかのようです。
このとき、BIは、決して所得と労働とを切り離して考えているわけではありません。
不可能になった労働、そしてそのための所得機会の喪失を補填し、生活に必要な原資とする貨幣を給付する社会保障・生活保障としての給付です。
この時に、ベーシックサービスがどうこう、という議論・意見はほとんど見られません。
『未来の再建』も『ベーシックインカムを問いなおす 』も、コロナ禍発生前の執筆です。
今発刊するならば、コロナ禍とBSとをどう関係づけ、BIをどう評価して記述するでしょうか。
この小論の最後に「ポスト・キャピタリズム」におけるBI論を、その代表的論者の主張を用いて説明しています。
まあ、一読しておく価値はあるかと思いますが、どちらかというと革命思想的な内容なので、なんとか2030年頃までに実現の目処を立てたいと思う者としては、関わっておれない、関わる必要がないと思いましたので省略します。
で、結局、佐々木氏の総括にあたる文面を決められなかったので、次回の井出氏の『未来の再建』におけるBS論への対論に、持ち越すことにします。
-----------------------------
本稿は、WEBサイト https://2050society.com 2020年11月15日投稿記事 2050society.com/?p=2557 を転載したものです。
当ベーシックインカム、ベーシック・ペンション専用サイト https://basicpension.jp は2021年1月1日に開設しました。
しかし、2020年から上記WEBサイトで、ベーシックインカムに関する考察と記事投稿を行っていました。
そこで、同年中のベーシックインカム及び同年12月から用い始めたベーシック・ペンションに関するすべての記事を、当サイトに、実際の投稿日扱いで、2023年3月から転載作業を開始。
数日間かけて、不要部分の削除を含め一部修正を加えて、転載と公開を行うこととしました。
なお、現記事中には相当数の画像を挿入していますが、当転載記事では、必要な資料画像のみそのまま活用し、他は削除しています。
原記事は、上記リンクから確認頂けます。